子どもオンブズ・コラム 令和7年7月号 子どもの自殺への対策を社会全体で取り組む
ページ番号1022612 更新日 令和7年7月7日 印刷
子どもの自殺への対策を社会全体で取り組む
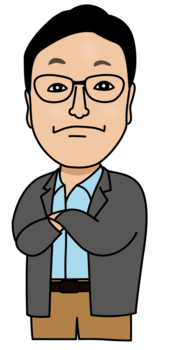
2025年6月5日、子どもの自殺への対策を社会全体で取り組むことを明記した改正自殺対策基本法が、衆議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。改正自殺対策基本法は、近年、増加傾向にある子どもの自殺への対策を社会全体で取り組むことを明記したものです。
この法律案は「こどもの自殺が増加している状況などに鑑み、こどもに係る自殺対策について基本理念に明記し、学校の責務を明らかにするほか、こどもに係る自殺対策の協議会について規定するとともに、基本的施策の拡充などを行おうとするものであり、(中略)基本理念として、デジタル社会の進展を踏まえた施策の展開及び適切な配慮について明記するとともに、こどもに係る自殺対策について社会全体で取り組むことを基本として行われなければならないこと」(衆議院厚生労働委員会 自殺対策基本法の一部を改正する法律案より)などを明記しています。本コラムでは、近年子どもの自殺数はどのようなかたちで増えているのか、どうして子どもの自殺への対策を社会全体で取り組まなければならなくなったのか、という点について、私が、日頃活動している自立援助ホームでの経験をもとに考えていきます。
子どもの自殺数について、厚生労働省は2025年3月28日に最新のデータを公表しています。全体を見れば、2024年の年間自殺者数が20,320人(確定値)で、前年より1,517人減り、1978年の統計開始以降2番目に少なくなっています。一方、小中高生は前年より16人多い529人となり、統計のある1980年以降最多となりました。男子は2年連続で減り、女子は2年連続で増えた結果、女子が初めて男子を上回りました。つまり、日本国内の自殺者数は2012年以降減少しているのに、小中高生の自殺数は増加を続け、しかも2024年には男女比が逆転したのです。このことについて福祉新聞(2025年4月7日)は「自殺した子どもの内訳をみると、女子中学生と定時制・通信制高校の女子が大きく増えました。高校生の自殺者数は全日制が多いが、自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は定時制・通信制が全日制より高いことが2023年3月の有識者会議で判明しました。女子中高生の自殺原因として男子よりも顕著に多いのが『健康問題』です。うつ病をはじめメンタルヘルスの課題が背景にあるとみられています」と述べています。
さらに、日本の子どもの自殺はグローバルな視点からはどのように見えているのでしょうか。UNICEF(国際連合児童基金)イノチェンティ研究所が、「予測できない世界における子どものウェルビーイング」というレポートを2025年5月13日に発表しました。そのレポートによると日本の15歳から19歳の自殺率はユニセフが調査した43カ国中上位から4番目だったようです。「特に、増加が顕著なのが、2019年から2020年であり、ここにコロナ禍の影響がある可能性が強いことは否めないであろう。さらに、子どもの生活においてコロナ禍の直接な影響(休校や行動変容など)がほぼなくなった2024年においても、子どもの自殺率が、高水準で、かつ増加していることは大きな問題である」と述べています。
以上の国内外のデータや報告をまとめると、女子の自殺が増えていること、とくに中学生と定時制・通信制高校の自殺率が上昇していること、急増のきっかけはコロナ禍の時期と重なり、2024年以降も女子をとりまく環境は継続しているということになります。これらは、社会的養護の現場の肌感覚と一致しています。
5年前、2020年早春に発生したコロナの世界的流行は、子どもたち全般に大きな影響を及ぼしました。なかでも自立援助ホームなど社会的養護の子どもたちの日常生活を一変させました。平時においてすら不安定な生活を強いられていた子どもたちは、国の自粛要請などによって、2020年2月末の早い段階から就労機会を失うなど一気に問題が顕在化しました。感染拡大とともに、社会のあらゆる場面で感染拡大防止が最優先されるようになったことで、子どもたちは様々な行動や活動が制限されました。アルバイトや通信制高校の継続に支障が生じただけではなく、好きなアーティストのライブやハローウィンの仮装パーティなどが中止になり、様々な社会体験の機会が奪われました。不適切な養育を受けてきた子どもたちは、密室のような家庭環境から逃れ、自立援助ホームにたどり着きます。東京や岐阜県から逃げてきた女子もいました。子どもたちに、心理的ストレスが高まり、気分障害、不安障害に相当する心理的苦痛を感じるものもあらわれ、自立援助ホームのスタッフは、「コロナ鬱」・自律立神経失調症、リストカット(自傷行為)やOD(オーバードーズ)、希死念慮への対応に追われる日々となりました。
コロナ禍以降、自立援助ホームへの入居相談では、近親者からの性虐待や性暴力被害に関する事案が増えています。X(旧Twitter)やLINEなどのアプリを使って買春者と出会い被害にあった子どもを、警察と連携して位置情報を把握できたことで保護したケースがありました。その子どもは、産婦人科医院にて緊急避妊ピルを処方していただき、性感染症の検査も受けました。これまでも保護者や親族から性被害をうけてきた子どもたちへのトラウマケアに取り組んできました。現場感覚では、女子の自殺の増加は、貧困、虐待などの迫害体験、性被害などと関連性が高いのではないかと感じています。格差拡大のなかで、子どもたちの生きづらい状況は続きますが、なかなか日本社会の中で問題化されにくいかもしれません。
2024年度の当自立援助ホームへの入居相談は、男子ホームが27件、女子ホームが38件で、3年連続で増加しており、兵庫県内からも相談を受けることがあります。前述のデータのように、コロナ禍がおさまっても、ここ数年の特徴として、希死念慮の強い子ども・若者の入居相談が寄せられたり、自殺企図を経験した子どもを受け入れたりしています。先日も救急車を呼びながら、この子ども自殺の問題を出口のところで対応するのはもう限界ではないかと感じています。個別の課題を社会全体の課題と捉え、国や自治体が予防活動にもっと積極的に取り組んでほしいというのが正直な気持ちです。
改正自殺対策基本法では、子どもの自殺対策について自治体の役割が明記されています。本法律では、内閣総理大臣や文部科学大臣、厚生労働大臣が関係機関と緊密に連携して施策を推進するとしたほか、学校も子どもの心の健康を保つために健康診断や保健指導などを行うよう努めるとしています。また、自治体は守秘義務を課したうえで、学校や医療機関、民間の団体などと情報を共有して対策や支援を行う協議会を設置できるとしています。このほか、国や自治体は、自殺しようとした人に継続的な支援を行い、遺族に対しても生活上の不安が緩和されるよう支援するなどとしています。
川西市子どもの人権オンブズパーソンは、1980年代以降、学校内外でのいじめなどを背景とした子どもの自殺が全国各地で起こり、大きな社会問題となっている中で、子どもの人権を守るための第三者機関などの仕組みの必要性が提起され、1998年制定されました。今回改正自殺対策基本法ができた機会に、あらためて1995年に川西市教育委員会が「子どもの実感調査」をもとに提出された「子どもの人権と教育についての提言」をふりかえり、子どもたちの「私事的・個人的な問題」を「社会的・公的な支援の課題」へとつないでいくことができるよう子どもたちのSOSを受けとめ、オンブズワークに取り組んで行きたいと思います。
執筆 オンブズパーソン 浜田 進士
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子どもの人権オンブズパーソン事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1235 ファクス:072-740-1233
子どもの人権オンブズパーソン事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。