子どもオンブズ・コラム 令和6年6月号 子どもの最善の利益にそったしくみを ~児童虐待で増える住所の非公開~
ページ番号1019856 更新日 令和6年6月28日 印刷
子どもの最善の利益にそったしくみを ~児童虐待で増える住所の非公開~
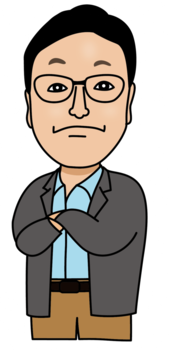
「ホーム長!ちょっと聴いてや。採用された会社の近くに引っ越そうと、市役所に支援措置の手続きに行ってきてん。そうしたら、『先に警察署に行って』と言われ、警察署に行ったら『まずは市役所に行って下さい』とたらい回しにされてん。ほんま腹立つわ」
これは、私がホーム長をつとめる自立援助ホーム「あらんの家」の卒業生Aくん22歳のLINE電話による訴えです。全国の自立援助ホームでは度々起きる出来事です。
Aくんによると、実父の虐待から逃れるため支援措置の手続きを申請しているのに「今でも、被害を受けているのか」と詰問されたり、「男性なのに」と性別に絡む発言を受けたりすることで、二次被害が起きたようです。「再出発しようと思って引っ越したのに、めちゃくちゃ悲しかった。なんで何度も傷つけられないとあかんの?こんなんやったら、前みたいにホーム長といっしょに市役所に行ったらよかったわ」
Aくんは、17歳から自立援助ホームで暮らし、退居後、給付型奨学金を受けてなんとか大学に通い、4年間で卒業しました。幼少期より実父から虐待を受けてきたため、引っ越し先を知られたくないと、住民基本台帳事務における支援措置申出書を転入先の市役所に自分一人で問い合わせたところ、上記のような経験をしたわけです。
私たちが、通称「支援措置」と呼んでいる住民基本台帳事務における支援措置とは、DVやストーカー、児童虐待の被害者らを保護する制度で、住民票などの閲覧や交付を制限することができます。総務省によると、支援措置の対象は2023年12月時点で8万3916件。虐待やDVが社会問題化する中、この10年間で2倍以上の数字となっています。
自立援助ホームとは、虐待や貧困などの理由に家族と暮らす権利をはく奪された子どもが生活をする社会的養護施設のひとつです。児童養護施設や里親との違いは、15歳以上を対象としていることと、就労自立をめざすことです。
子どもたちの入居理由は、身体的虐待、ネグレクト、性暴力被害、児童労働、ヤングケアラー、高校に通学させてもらえない、家出、妊娠・中絶による高校中退、保護者の養育放棄、迫害体験による自殺企図など様々です。私たちは児童相談所や警察から子どもを預かるとき、保護者の同意が得られない場合は、子どもの意見を聴き、委託契約を結びます。そして、その子の行き先を探している保護者から子どもたちの権利を守るため、市役所で支援措置手続きを子どもに同行して行います。手続きが完了すれば転居先は本人にしかわからないことになります。
この支援措置には、児童相談所や管轄内の警察の意見書が必要となります。この意見書を書いてもらうよう申出書を作成するのが、私たち自立援助ホームの仕事です。子どもから詳しい事情を聴き、児童相談所や警察に意見書を作成してもらいます。その意見書をもって市役所に行くと、私たちは特別に会議室に案内されて、秘密を守ってもらいながら手続きを行います。子どもたちは「少し安全を確保できた!」と表情が柔らかくなります。しかし、この支援措置の効力は一年間しかありません。自治体によっては一年ごとに児童相談所あるいは警察の意見書が必要となります。私の自立援助ホームがある奈良市の場合、2年目以降は必要ありませんが、川西市の場合はどうでしょうか。また、転居する場合は、今回のAくんのような問題が発生します。
私は、子どもの権利条約とこども基本法の理念に基づき、子どもの最善の利益の観点から支援措置の更新手続きを適正化してほしいと願っています。被害を受けている人にとっては手続きの負担が大きいことが課題です。退居後18歳を過ぎても、彼女彼らは引き続き支援措置を必要とします。児童相談所によっては18歳以降も意見書を書いてくれるところもありますが、20歳を過ぎるとだんだん警察にお願いすることが増えてきます。彼女彼らは更新の度に、自らの虐待体験を語らねばならず傷つきます。Aくんのように、自治体間の連携が悪く、たらい回しにされることもあります。時間のズレや細かなミスで保護者に居場所がばれてしまい、アパートまで来られてしまったこともあります。支援措置の適正化は子どもたちにとって命にかかわることなのです。
私が運営する自立援助ホームでは、この11年間で15件を越える支援措置手続きをしてきました。自立援助ホームだけではなく、児童養護施設、里親など全国の社会的養護関係機関でも、この支援措置の手続きの適正化が大きな課題となっています。 たとえば、私自身は次のような適正化案を考えています。支援措置の1年ごとの延長手続きには児童相談所などの意見書が必要ないように、各自治体間で共通のルールを作ってほしい。できることなら、過去の被害は変わらないのだから、毎年の更新をなくしてもらいたい。Aくんのように行政の窓口では「まず警察に行って」と言われるケースが多いので、たらい回しされないように、支援措置についての行政手続きマニュアルみたいなものを作ってほしい。
児童虐待が起きている現場で、子どもの声を聴いていると、私が暮らす自治体にも子どもの人権オンブズパーソン制度があったらと思うことがあります。Aくんのようなたったひとりの子どもの声からも、子どもの権利をめぐる制度的な課題が浮かんできます。なぜなら、ひとりの子どもの権利侵害には、私たちおとながつくってきた様々な課題がその子どもへの虐待被害という形であらわれるからです。もし、オンブズパーソンがあったとしたら、加害の保護者が問われるだけではなく、私たちの社会制度そのものが子どもたちを苦しめていることを明らかにできるのではないかと考えます。
子どもの人権オンブズパーソンは、Aくんのようなたった一人の子どもの声から、子どもを代弁して、しくみを変えるチカラを持っていると思います。被害を受けてきた子どもたちが、加害者から追跡されるのではと怯えることなく、安心して生活できるように願っています。
執筆 オンブズパーソン 浜田 進士
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子どもの人権オンブズパーソン事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1235 ファクス:072-740-1233
子どもの人権オンブズパーソン事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。