〔子どもオンブズコラム平成30年5月号〕最近のケースに接して思うこと
ページ番号1006972 更新日 平成30年5月8日 印刷
最近のケースに接して思うこと
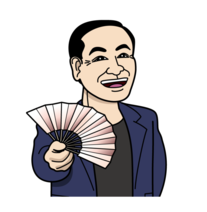
ここ数年の相談内容の傾向をみてみますと、家庭生活や家族関係に関するものがその割合の1位を占めています。今回は、家庭生活や家族関係に関し、普段の活動の中で感じたことを親の視点から考えてみたいと思います。
家庭生活や家族関係に関する相談の中でも最近のケースでよく経験するのが、親の気持ちが先走ってしまい、それが行動として現れ、ややもすると子どもの思いがなおざりにされているというものです。このような現象が起きてしまう一般的な原因としては、親が子どもになるべく平坦な道を歩ませてあげたいと思う気持ち、子どもの思いが親に伝わりにくくなっているという親子間のコミュニケーションの問題、社会的背景としては、子どもの数が減り、子どものことにより時間を割けるようになったことなどが考えられるかもしれません。
家庭生活や家族問題といった場合、このようなケースに限らず、親が子どもの行動をどう受け止めていいのかわからない、子どもとのコミュニケーションがうまくいかない、地域の中でも孤立してしまいがちになるなど、親御さんにも支えがあった方が望ましいと思われるケースもあります。
ただ、ここでは、私なりにではありますが、前述のようなケースを考えてみたいと思います。
親の思いが先走りがちなケースでは、親の方は、子どもが何もしないと手遅れになる、子どものやり方だとうまくいくはずがない、自分がちゃんとしてあげないといけないと思ってしまいます。そして、子どもの気持ちを聞く前に自分の判断のみで行動に移してしまいます。
しかし、「手遅れになる」、「うまくいくはずがない」などというのは、一体、誰の不安でしょうか。それは、やはり親の不安ということになりますから、親が自分の不安を解消するために行動に出たという面は否定できないと思います。
でも、果たして、その行動は子どもの成長にとってプラスになっているのでしょうか。また、子どもが本当に望むものなのでしょうか。そうでなかった場合、子どもが親の行動をどういう思いで見つめるのかを考える必要があるように思います。
子どもは、自分自身で問題を解決していく力をもっています。子どもが何らかの問題に直面した場合、まずは、子どもを信用して、子どもの行動を見守ることが大事ではないでしょうか。決して、放任するということではありません。親が行動する場合も、少なくとも、「こうしようと思っているけど、どうかなあ」と、子どもの気持ちをしっかりと確認する必要があるように思います。私たち大人も、周りの人がよかれと思って自分のために動いてくれた場合、そのこと自体はありがたいと思っても、「自分でこうしようと考えていたのに」と感じたことはないでしょうか。
子どもの問題に関する親の不安は、大人として親自身が自分の中で引き受ける勇気をもつことが必要だと思います。そして、そのことが子どもの自立に向かう成長につながるはずです。
最後に、私が愛読している河合隼雄さんの本から引用させていただきます。
『われわれは子どもに対するときに、全体をうまく操作して「よい子」に仕立てあげようとか、どのようなことを教えこもうとするのではなく、一人ひとりが異なる存在であり、その個々の子どもが大人の測り知れないものを内に蔵していることを認識して会っているだろうか。』
『われわれが考えねばならぬことは、・・・教師、親、すべての大人が、もっと子どもの自由に伸び伸びした行動を保障し、見守ることに努力することではなかろうか。子どもたちに対する親の干渉が強すぎるのだ。』
『日本の親の各人が、子どもの真の幸福について考え直すことが必要である。大人が子どものために幸福の路線を敷くのではなく、子どもたち自身が試行錯誤しつつ、自分の力で道を探していくのを許容し見守る態度をもたねばならない。』(「より道 わき道 散歩道」より)
執筆:オンブズパーソン・吉川法生(きっかわのりお)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子どもの人権オンブズパーソン事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1235 ファクス:072-740-1233
子どもの人権オンブズパーソン事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。